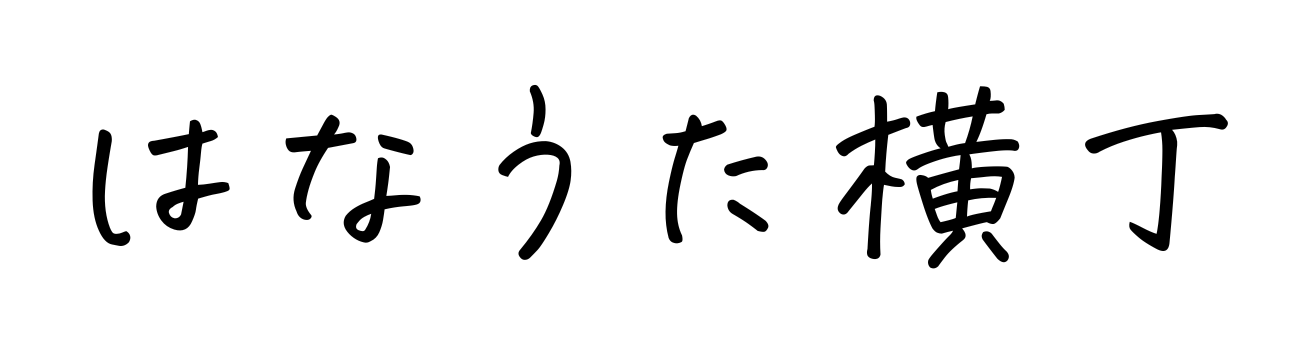春と夏のあいだ。
どちらかというと夏の気候に近づいてきたこの季節になると、夜にふらふらと散歩にいきたくなる。なんだろうかこの徘徊癖。昔っからだ。
徘徊しながらなにをしているのかと言われれば「ぼーっとしている」と答えるしかないのだけれど、その「ぼーっと」のなかに多くの感情が巡っていたりする。公園のベンチ、左手には缶コーヒー。夜空に浮かぶ月をみていると聴きたくなる音楽がある。エレカシの「今宵の月のように」という曲だ。
ぶわっと脳内に文字が浮かんでくるので、文章沼に浸って思うままに筆を滑らせていく。
くだらねぇと

くだらねぇと呟いて 醒めたツラして歩く
いつの日か輝くだろう 溢れる熱い涙
いつまでも続くのか 吐き捨てて寝転んだ
俺もまた輝くだろう 今宵の月のように
なにもかも「くだらねぇよ」そんな風に思っていたときがある。あの日あの頃、青春時代、今では好青年である僕も(?)そんな時期があった。目に見える世界が急につまらなくなって、人生をなんだか悟っちゃって、全部に冷めていた時期があった。きっと、不器用だったんだとおもう。中学生の頃であった。
自分がしていることが何ひとつ伝わんなかったんだ。想っていることが何ひとつ伝わらなかった。全部自分のせいなのに、そんなことも分からずに「なんで伝わんないんだよ」という具合に悔しさがこみ上げ、いつしか冷めていた。「伝わんないならもういいよ」って。カッコつけたかったんだ。というより、そうでも思わなきゃカッコがつかなかった。愛を勘違いしていたんだ。ひねくれていて、うまく受け取れなかった。
愛を探しにいこう

明日もまたどこへゆく
愛を探しにいこう
もう二度と戻らない日々を
俺たちは走り続ける
愛がほしい時期があった。自分が愛されている実感がほしい時期があった。この「愛の確認作業」みたいなものがすんなりできればいいものの、当時のぼくはそんな勇気は持ち合わせておらず、大切な人を傷つけたりもした。愛されているのに、知らんぷりをして、強く当たって、もっと与えられるのを待った。そんな両親への反抗期みたいなものが、小さいけれど僕にもあった。両親に聞くと憶えてないと言うかもしれないけれど、たしかにあったんだ。
そうやって手探りで愛を探した結果、それは意外にもすでに腕の中にあって、「あるんなら早く教えてくれよ」と言わんばかりにニヤけそうな口元を押さえた。「どこにあるんだよ」と思っていた幸せが、気付いたら腕の中にあって、こんなに抱きしめられる。その喜びと感謝を文字にして、封筒に入れて、成人式の日に両親に渡した。
いつの日か輝くだろう

いつの日か輝くだろう
今宵の月のように
いつの日か輝けるだろうか。こんな僕でも輝けるのだろうか。全然ダメだけど、なんにもできないけど、こんなに愛されてるならさ、輝かなきゃだめな気がするんだ。申し訳が立たない。家族や友達といわれる人たち、周りにいてくれる人たち、そんな人たちにさ、抱えきれないほどの愛をもらった。一人じゃなかったんだよ。本当だ。
いつもより月が明るい。輝きたいな、あんな風に。輝けるかな? ちょっと怖えな。まあ、なんとかなるか。ってな調子でいつもやってきた気がする。いつかどうしようもなくなるときが来るんだろうけど、しばらくはこのまま進んでみるよ。助けてね。よろしく頼むよ。なんて言いながら自立しない僕はまだまだどうしようもない子供だ。元気かピーターパン。
自分のダメなところなんてポンポン浮かんでくる。夜はとくに弱くなるんだ。でもそんな自分を変えるつもりもないし反省する気もない。弱いけど、弱いから、肯定する。こんなろくでもない夜が似合う自分が、ちょっと好きだ。
飲みほした金の微糖をベンチに置いて空を見上げる。月の明るさが心を洗う。平凡でつまらない人生だ。そんな人生を誰よりも愛した僕がいる。ちっぽけな物語だけどさ、いつの日か輝くだろう。今宵の月のように。